ゾウのベハティとネズミのザワディ

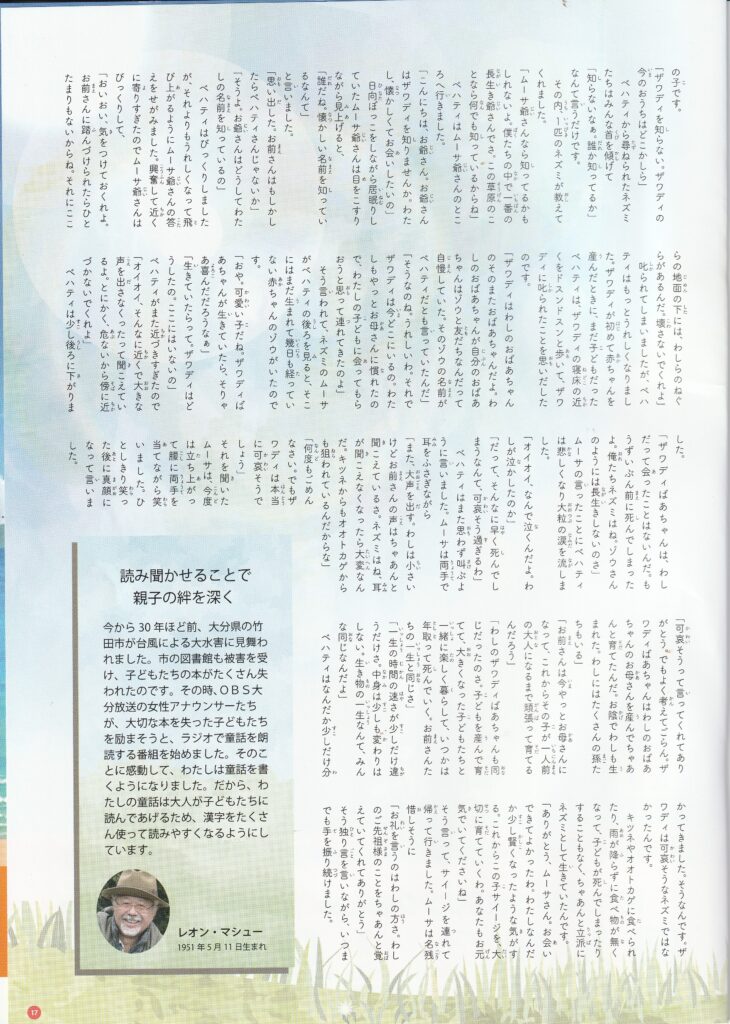
大方の日本企業が固唾を飲んで見守る中、マッドマンが日本へ30〜35%の関税をかけると言い出した。防共協定(日米安保条約)を結んでいる同盟国のはずの国の経済を弱体化して、それが戦略上米国ファーストになるのかどうか、まともな脳みそなら分かるはずだが。それとも防共協定はもう必要ないというのだろうか。それならそれで大いに結構、米軍にお引き取り願おう。マッドマンに言われなくても、日本は自分の国は自分で守らなくてはならない。2022年段階で世界第5位(現在は第7位)の軍事力を誇る日本なのだから。
そこで思い出されるのが美空ひばりだ。何を唐突に訳のわからないことを言うと思われるかもしれないが、美空ひばりの「お茶漬けサラサラで生きていく」と言う言葉を覚えている日本人がどのくらいいるだろうか。
1973年、弟の暴力団との繋がりを理由に、それまで10年連続でNHK紅白歌合戦のトリを務めていた彼女が落選したのだ。その時の会長、当時の郵政省事務次官を退職して天下った小野吉郎の決断だった。それまでは公然の秘密扱いで周知されていた山口組総長とひばりの関係もマスコミに取り上げられるようにもなった。ついでながら1976年、小野吉郎自身はロッキード事件で有罪となった田中角栄との関係を取り沙汰されて会長を辞任に追い込まれた。政府高官の権力を振りかざしたダブルスタンダードの典型例だ。
美空ひばりは紅白落選後、NHKと断絶して総ての番組に出なくなった。「NHKを相手に喧嘩したら飯が食えなくなる」と多くのファンは心配した。確かにその後、全国の公共施設が美空ひばりに会場を貸さなくなった。その時に語ったのが「お茶漬けサラサラ」である。「もともと貧乏には慣れている。収入がなくなったら、亡くなったで、元の貧乏家族に戻って家族でお茶漬けサラサラ食べながら生きていけばいい」と言ったのだ。当時22歳のわたしは、それを聞いた時、心の底から嬉しくなったことを今でも思い出す。理不尽な扱いにただただ首を垂れて「生活のためだ」などと言い訳をする輩の多い時代に、なんと爽やかな覚悟だろうかと感心したのだ。その後、NHK相手のひばりの戦いは彼女の勝利で終わる。1976年に小野吉郎会長が自身のスキャンダルで辞任すると、翌年、NHK側の三拝九拝に応じる形で歌謡番組に復帰し、1979年の紅白30周年記念大会に特別出場を果たす。
なぜわたしがそこまで感激したかと言うと、当時も日本は米国からの理不尽な日本製品ボイコットの嵐に見舞われていたからだ。笑えるのは1971年に米国で成立したマスキー法だ。法律そのものは表向き米国の大気を自動車の排気ガスから守ろうと言う立派なものだったが、本音は日本車締め出しを目的としていた。しかし、マスキー法の基準をクリア出来たのは結局日本車だけで、米国のビッグスリーはロビー活動を駆使して、法律を長い間棚上げ状態にしてしまった。日本はその基準をクリアするために必死の努力をして、結局、ホンダがレシプロエンジンでは当時世界一燃費の良いCVCCエンジンを実用化して、排気基準をクリアした。その時からロビー活動だけに頼って企業努力を怠ったビッグスリーの凋落が始まったのだ。
今回もマッドマンが大統領に返り咲いたおかげで、理不尽な要求を突き付けられている。本音がどこにあろうと、世界経済の常識も、市場経済の原則も無視する理不尽な政策は早晩破綻する。ここは日本企業にも、国民にもここは美空ひばりの断固たる覚悟が求められているのではないだろうか。
少し冷静になって計算してみると、今回の米騒動も不思議な現象ではないかと思えてくる。2024年の、つまりわたし達が今食べているコメについての農水省の公式発表では水田の総面積は前年度比0.7%(1.6ha)減の231.9万ha、収穫量は734.6万トンということである。最近は減反政策の終了後も、年々田の面積は減ってきたが、それでも収穫量は令和3年756.4万トン、令和4年727.0万トン、令和5年716.6万トンと、700万トン以上で推移してきた。
同じ、農水省の統計では日本人のコメ消費量は一人当たり年間50.9㎏、これに令和7年4月現在の日本の人口は1億2340万人をかけると628.1万トンになる。これに日本酒の原料米分約20万トン(令和4年)を入れても、差し引き106.5万トン余る計算になる。インバウンドの消費分も昨年のように3686万人も来るとなると無視はできないだろう。そこでこれも計算してみると、昨年のインバウンドの日本滞在日数は平均で3.08日、一人一食200g、一日に2食米飯や寿司を食べたとして、年間でせいぜい7万トンだ。コメの輸出量も計算に入れるとして、援助米を除くとコメとその加工品(日本酒や煎餅など)を含めて約5万4千トン。
いずれにしても差し引き56万トンは余っている計算になる。これにさらに備蓄米の緊急放出が何十万トンある。これで未だにコメが市場に出てこないということは、誰かがどこかで隠しているということになるのではないか。何度も言ってきたように、今回の米騒動はトランプ関税交渉でコメの輸入量を増やすことになることを考えて、あらかじめ世論を操作しておこうという目論見があったのではないか。それをやらせるために協力してくれているノウーキョーやゼンノーに、一度高騰したコメを売り逃げる時間的余裕を確保しなくてはならなかったからこそ、大騒ぎになってもコメが市場に出てこなかったのではないか。そこにペテン師ジュニアが登場して、古古米どころか古古古米まで売りさばこうということになったのだから、どこかでコメを持っている誰かさんは慌てていることだろう。
食管法が廃止され、減反政策を方向転換した以上、国は米価に対して影響力を持たなくなったし、持ってはいけないはずなのだ。そもそも主食のコメとはいえ市場原理に委ねるのが本筋だろう。影響力を放棄すべきところを、生産者の声に耳を貸すふりをして、それをしてこなかったのは自民党政治の無能さの証左である。
もちろん、コメは永い歴史的経緯を経てこの国の主食となり、ステイタスシンボルであり、文化や伝統の基礎に組み込まれてきた。今日でも農業の中心はコメであると言っても過言ではあるまい。しかし、日本の自然環境や地理的、地勢的特性からして、コメの生産性は世界水準から見れば実は宿命的に低い。ササニシキに代表されるようなブランド米だと言っても、それはあくまで日本の国内市場の反映であって、一部の大金持ちの物好き相手はともかく、国際市場の常識的な価格で勝負のできるものではない。
それでもわたしが米作を日本の農業、日本の農政の中心に据えなくてはならないと主張してきた。、稲作はもはや単に主食の確保、食糧自給率確保のためにあるのではないのだ。稲作はこの国の2千年以上の歴史の中で、治山治水と表裏一体の発展をとげ、わたし達の生活を根底から支える国土保全、環境保全のための必須要件となっているのである。
だからといって、民主党時代に所得補償制度が論議された時、わたしは農業の本質、農業者の本音を知らない「おまち育ち」の政治家のいうこともうまくいかないと思っていた。ではどうすればいいと考えているか、詳しく述べてみたい。
コメは国防の要
米価をめぐる騒動は小泉新農相の登場でメディアは大はしゃぎだし、自民党は参議員選挙を前にして人気回復となると期待しているようだ。「令和の米騒動」というが、本質的には「昭和のトイレットペーパー騒動」と変わらない。米価など食管法がなくなった今日、市場経済に任せておけばいいことである。不作になったからといって、生活を守るために、いつもより一袋多く買った消費者の心情は許されるとしても、まだ売っていなかった生産者の出し渋り、全農始め流通の各段階での思惑買いやコメ隠し、ましてや買い占め他業者などに「濡れ手に粟」の儲けは許してはならないのだが、それさえも政府が愚図々々している間に高値のまま売り抜けるかも知れない。
ペテン師ジュニアの「コメの小売価格は5キロ、2000円」という選挙を意識した派手な事前運動キャンペーンにも腹が立つが、自民党農林族のドン森山幹事長の発言には呆れてしまう。曰く「生産者がいてはじめて米ができることを忘れてはいけない。安ければ良いというものではない。再生産していける価格こそ自民党の目指す方向性だ」というのは、一見まともなことを言っているように聞こえるが、いくら党の県連での気炎だったとしても、まるで他人事のような物言いに腹が立てなくてはならないのは当の生産者ではないだろうか。
消費者もメディアも米価にばかり気を取られているが、米作、ひいては日本の農政の問題の本質はそこにはない。日本の農家の内、大規模農業をやっている事業体は農業者全体の20%もいないのに、その大規模農業者の米生産量は逆に全生産量の8割近くに上っている。自民党が票田にしているのは残りの零細農家であり、霞が関の農林官僚が天下る先は農協と全農、農林金庫である。今回の米価高騰にしても、昨夏の天候不順を幸いとして、政府が意図的に誘導した結果だと考えている。現に日米関税交渉の既にコメの輸入拡大というカードを切っているという。現政権は農業者重視と口にしながら、実際はこれまでと同じく農業者を裏切って、場合によっては日本の農業にとどめを刺してもいいと考えているようだ。。
繰り返すが、森山幹事長の発言はとても責任政党の幹事長の、それも農林族のドンの発言とは思えない。これまであらゆる局面で農政をほったらかしにしてきたどころか、改革や刷新のチャンスのたびに農林族と農協はタッグを組んで、結果として農地を潰し農家を流亡させてきたのはどの政党だったのか。とはいえ、その政党を岩盤支持層として支えてきたのも当の農業者なのだから、話しは単純ではない。
米の生産と流通は単なる食糧自給という農業問題に留まらない。それどころか国家安全保障の問題として捉えなくてはならない課題である。わたしがこれまで何度も言ってきたことだが、国の安全保障は、国民の生命財産を守り、次世代の将来へ夢をつなぐことにあり、そのために平和を維持することにある。だからこそ食糧の自給、国土の強靭化、環境の保全の三要素こそが、安全保障の根幹であると、わたしは考え、それを常に発言してきた。徒に武器を増強し、兵力を増やすことはかえって国民を戦争の惨禍に引き込む道筋でしかない。軍事力による平和の維持などというのは悪魔のロジックであり、現政権のように財源配分の最優先項目に軍事・国防予算を置いている状態を続ければ、やがて昭和初年のようにポイント・オブ・ノーリタ―ンを通過して、わたし達の子や孫を地獄に落としてしまう。
今、最も優先すべき安全保障の根幹は農業である。農業は食糧だけでなく農業の持つ治山治水の一面を通して国土保全の根幹である。さらには食糧を野放図に輸入することは環境破壊と、保健衛生面での侵害に通じているのである。それを単に自党の票田としてのみ考え、農協を通してアメとムチで生産者を縛り、世論を操作し、輸出産業の生産活動を守るために国民を騙し続けてきたのは誰なのか、もう一度わたしたちは考えなくてはならない。さあて、この国の有権者は今夏の参議院選挙でその考えをどう形にするだろうか。
―続く―
巡り巡って故郷に帰ってきた。湯けむりと硫黄の匂い、屏風のような山々に囲まれてこの町で育ち、18歳で上京し24歳で地球の裏側に渡り、夢のような日々を送った。1995年に帰国して、それから28年大分市で大分市民のために働いた。少なくともそのつもりだった。長くもない人生の果て、元のように無一文ではあるけれど、とにかく終の棲家となるであろう故郷に帰ってきた。
子どもの頃から縦横に慣れ親しんできた「国際観光都市」「東洋のナポリ」である。遥か昔を懐かしみながら改めて歩いてみたい。
どんな心象スケッチが描けるか楽しみにしながら、さあて、どこから始めようか。
昨日の本人と首相の発言では辞職も更迭もなかったのが、急転直下、江藤拓農林水産大臣が切られることになった。後任はペテン師ジュニアの小泉進次郎の名前が取りざたされているらしい。流石の自民党も選挙前の参議員たちに迫られて、トカゲの尻尾を切らざるを得なかったのだろう。国民の怒りがここまで膨らむと想像できずに高をくくっていた石破首相の政治感覚にも疑問符が付く。政治感覚の無さということでは国民民主党の玉木代表もなんでわざわざ「辞任は求めない。結果を残すことに期待する」なんて聞かれもしないのに、エールを送ったのか理解に苦しむ。こちらもこの発言で進退問題にならないのが、国民民主党の不思議なところだ。
そんな中、赤澤特使が渡米する。まさか、参議院選挙前に、コメ輸入拡大のカードを切るほど馬鹿ではないと思うが、選挙が終われば総辞職にでもならない限りコメの輸入拡大ということになるだろう。日本の農家はまた、減反や他品目への転換を迫られるし、農地は確実に減っていく。農地が減るということは、平地では問題は少ないが、中山間地や急勾配の地域では、農地の荒廃イコール災害である。
この国の政権党が誰を見て、どこを見て政治をしているか、今更ながら、わたしたちは良おーく考えなくてはならない。しかし、ここでも選挙そのものを金にしようと立候補したり、フェイク情報で撹乱しようとする輩が跋扈しているし、それに乗せられる野次馬有権者の存在もある。野次馬というのは関係のない人間が興味本位で騒ぐということだが、この国の国民である以上、関係のない人間ではない。野次馬感覚ということは自ら日本国民ではないと表明しているということのだが、嘆かわしいことにその自覚すらない。ネット上の野次馬たちにはそのことを思い知らせる必要もあるのだが、法整備は進まないし、石破首相はただ腕組みをして考えているふりをしているだけだ。
そうしている間にもこの国の軍国化は着々と進んでいる。今はまだ、大方の国民には聞こえていないだろうが、軍靴の足音が微かに微かに、それでも確実に聞こえているのだ。このままではその足音がどんどん大きくなって、近づいてくることになるのだが。